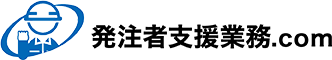建設情報コラム
2025-07-22
発注者支援業務は激務?残業事情と働き方の実態を探る
この記事は、発注者支援業務に興味がある方や、現在この業務に従事している方に向けて書かれています。
発注者支援業務は「激務」との声も耳にします。
実際に残業はどれくらい発生するのか、ワークライフバランスは確保できるのか。働き方の実態について詳しく見ていきましょう。
発注者支援業務は「激務」との声も耳にします。
実際に残業はどれくらい発生するのか、ワークライフバランスは確保できるのか。働き方の実態について詳しく見ていきましょう。
発注者支援業務とは?
発注者支援業務とは、国土交通省やNEXCO東・中・西日本、UR都市機構などの公共事業の発注者が本来行うべき業務(工事監理業務・資料作成業務・積算業務)を代わりに行う業務です。
代わりに行う組織としては、本業務を専門としている一般社団法人や民間の建設コンサルタント企業が該当します。
民間の立場でありながら、公共事業の品質と進行を支える重要なポジションです。
詳しい内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。
代わりに行う組織としては、本業務を専門としている一般社団法人や民間の建設コンサルタント企業が該当します。
民間の立場でありながら、公共事業の品質と進行を支える重要なポジションです。
詳しい内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。
発注者支援業務は本当に激務なのか?
発注者支援業務が「激務」と言われる背景には、いくつかの明確な要因があります。
中でも特に影響が大きいのが、業務が季節的に偏る傾向と、公共工事ならではの手続きの複雑さです。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
中でも特に影響が大きいのが、業務が季節的に偏る傾向と、公共工事ならではの手続きの複雑さです。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
年度末に業務が集中する背景
最も多くの現場関係者が口をそろえて挙げるのが、「年度末(1月〜3月)に業務が集中する」という点です。
公共事業は、国や自治体の予算制度に基づいて執行されます。
予算には明確な「年度区切り」が存在しており、原則としてその年度内に契約・着工・完了・精算までの流れを終える必要があります。
これは国の予算執行ルールであり、いかにスケジュールがタイトであっても、翌年度にずれ込むことは基本的に認められておらず、厳格に期限内の完了が求められます。
この制度上の都合により、1月から3月にかけて工事の完了検査や出来形確認、竣工書類の作成、支払い手続きなどが一気に押し寄せるのです。
実際、年度末になると、現場では以下のような業務が一斉に進行します。
・完了検査や部分検査への立会い
・写真整理や成果物のとりまとめ
・各種書類(変更契約、数量精算、設計変更)の作成
・電子納品の最終確認と提出準備
・発注者との打ち合わせや報告書の最終提出
その結果、平日の残業はもちろん、休日出勤が発生するケースも増加し、文字通りの「繁忙期」となるのです。
特に発注者支援業務を担う人は、工事業者とは異なり「発注者側の立場」で全体を見渡し、行政に準拠した正確な成果物を作成する必要があるため、作業の幅と責任も大きくなりがちです。
公共事業は、国や自治体の予算制度に基づいて執行されます。
予算には明確な「年度区切り」が存在しており、原則としてその年度内に契約・着工・完了・精算までの流れを終える必要があります。
これは国の予算執行ルールであり、いかにスケジュールがタイトであっても、翌年度にずれ込むことは基本的に認められておらず、厳格に期限内の完了が求められます。
この制度上の都合により、1月から3月にかけて工事の完了検査や出来形確認、竣工書類の作成、支払い手続きなどが一気に押し寄せるのです。
実際、年度末になると、現場では以下のような業務が一斉に進行します。
・完了検査や部分検査への立会い
・写真整理や成果物のとりまとめ
・各種書類(変更契約、数量精算、設計変更)の作成
・電子納品の最終確認と提出準備
・発注者との打ち合わせや報告書の最終提出
その結果、平日の残業はもちろん、休日出勤が発生するケースも増加し、文字通りの「繁忙期」となるのです。
特に発注者支援業務を担う人は、工事業者とは異なり「発注者側の立場」で全体を見渡し、行政に準拠した正確な成果物を作成する必要があるため、作業の幅と責任も大きくなりがちです。
公共工事の手続きの複雑さ
もう一つ見逃せないのが、「公共工事に関わる業務は非常に手続きが複雑である」ということです。
民間の建設業務と比べて、公共工事は契約・設計・積算・検査・精算のすべてにおいて、厳格なルールと審査基準が設けられています。
これにより、ミスが許されない高い正確性と、スピード感のある業務遂行の両立が求められます。
たとえば、「設計変更」が発生した場合を考えてみましょう。
・現地の条件変化や発注者からの要請により、設計を見直す必要が生じる
・該当箇所の仕様書や図面、数量計算書を修正
・単価再積算を行い、金額変更の根拠を明確にする
・発注者に説明・協議の上、必要な決裁を得る
・書類を整えて契約変更手続きを行う
これらの作業は、すべて公的な記録・監査に耐えうる内容でなければならず、かつ、工事の進行を止めない範囲で速やかに行う必要があります。
こうした事情から、発注者支援業務では常に「正確であること」と「納期を守ること」の板挟みになりやすく、現場のストレス要因にもなっています。
また、書類のフォーマットや記載ルールは発注者ごとに異なる場合もあり、それに対応するための知識やノウハウも要求されます。
結果として、技術力だけでなく、事務処理能力・対人調整能力も求められる高度な職種といえるでしょう。
民間の建設業務と比べて、公共工事は契約・設計・積算・検査・精算のすべてにおいて、厳格なルールと審査基準が設けられています。
これにより、ミスが許されない高い正確性と、スピード感のある業務遂行の両立が求められます。
たとえば、「設計変更」が発生した場合を考えてみましょう。
・現地の条件変化や発注者からの要請により、設計を見直す必要が生じる
・該当箇所の仕様書や図面、数量計算書を修正
・単価再積算を行い、金額変更の根拠を明確にする
・発注者に説明・協議の上、必要な決裁を得る
・書類を整えて契約変更手続きを行う
これらの作業は、すべて公的な記録・監査に耐えうる内容でなければならず、かつ、工事の進行を止めない範囲で速やかに行う必要があります。
こうした事情から、発注者支援業務では常に「正確であること」と「納期を守ること」の板挟みになりやすく、現場のストレス要因にもなっています。
また、書類のフォーマットや記載ルールは発注者ごとに異なる場合もあり、それに対応するための知識やノウハウも要求されます。
結果として、技術力だけでなく、事務処理能力・対人調整能力も求められる高度な職種といえるでしょう。
残業事情のリアル:どれくらい忙しいのか?
発注者支援業務は、工事の進行に合わせて柔軟かつ的確な対応が求められる仕事であるため、「残業が多い」「忙しい」といったイメージを持たれることも少なくありません。
では、実際にはどの程度の残業が発生しているのでしょうか?
ここでは、現場の声や業界の傾向をもとに、よりリアルな残業事情を詳しく見ていきます。
では、実際にはどの程度の残業が発生しているのでしょうか?
ここでは、現場の声や業界の傾向をもとに、よりリアルな残業事情を詳しく見ていきます。
実際の残業時間は?
発注者支援業務における残業時間は、所属する会社の方針、配属先の発注者、担当する業務内容、現場の規模や状況などによって大きく変動します。
そのため一概には言えませんが、以下のような平均的な傾向が見られます。
そのため一概には言えませんが、以下のような平均的な傾向が見られます。
| 時期 | 平均残業時間(目安) |
|---|---|
| 繁忙期(1〜3月) | 月40〜60時間程度 |
| 通常期(4〜12月) | 月0〜30時間程度 |
繁忙期にあたる1〜3月は、前述の通り工事完了や検査、報告書作成、積算変更の対応などが重なるため、残業が連日続くケースも珍しくありません。
中には土日出勤を要する場面もあり、「この時期は覚悟が必要」という声も多く聞かれます。
一方で、通常期の4〜12月は相対的に業務が落ち着く傾向があり、現場によってはほとんど定時退社が可能なケースもあります。
特に4月〜6月頃は新規案件の準備段階で、比較的ゆとりを持って働けるという声が多く聞かれます。
このように、業務量には“季節的な波”があるのが発注者支援業務の大きな特徴です。
メリハリのある働き方ができる一方で、忙しい時期には計画的な対応が必要となります。
中には土日出勤を要する場面もあり、「この時期は覚悟が必要」という声も多く聞かれます。
一方で、通常期の4〜12月は相対的に業務が落ち着く傾向があり、現場によってはほとんど定時退社が可能なケースもあります。
特に4月〜6月頃は新規案件の準備段階で、比較的ゆとりを持って働けるという声が多く聞かれます。
このように、業務量には“季節的な波”があるのが発注者支援業務の大きな特徴です。
メリハリのある働き方ができる一方で、忙しい時期には計画的な対応が必要となります。
残業代の支給と労働環境
民間の建設コンサルタント企業が担う発注者支援業務は、労働基準法に則って雇用契約が結ばれているのが基本です。そのため、以下のような環境整備が進んでいます。
▶残業代の支給体制
多くの企業では、いわゆる「36協定(時間外・休日労働に関する協定届)」に基づき、労働時間を適正に管理しています。
繁忙期においても、あらかじめ定められた残業時間の上限を超えないよう調整されており、残業代(時間外手当)は法定に基づいて支給されるのが一般的です。
会社によっては、以下のような取り組みも見られます:
・みなし残業制度の廃止:実働時間に応じた正確な支給を徹底
・勤怠管理システムの導入:勤務時間の記録と報告を電子化
・残業抑制インセンティブ:残業時間を抑えた社員に報奨金や表彰制度を導入
▶発注者側からの働き方改善の要請
発注者である国や地方自治体、NEXCOやUR都市機構といった機関も、過重労働の是正に積極的に取り組んでいるのが近年の傾向です。
その背景には、建設業界全体の人材不足、若手技術者の離職率の高さ、そして長時間労働による健康被害への懸念があります。
これを受け、発注者は次のような取り組みを強化しています:
・勤務時間のガイドライン提示:派遣職員の労働時間に上限を設ける
・業務分担の見直し:発注者内部の職員と業務の役割を再整理
・ICT化による省力化の推進:電子納品・リモート会議・ペーパーレス化など
これにより、「支援業務=激務・過酷」というかつてのイメージは、少しずつ解消されつつあります。
▶残業代の支給体制
多くの企業では、いわゆる「36協定(時間外・休日労働に関する協定届)」に基づき、労働時間を適正に管理しています。
繁忙期においても、あらかじめ定められた残業時間の上限を超えないよう調整されており、残業代(時間外手当)は法定に基づいて支給されるのが一般的です。
会社によっては、以下のような取り組みも見られます:
・みなし残業制度の廃止:実働時間に応じた正確な支給を徹底
・勤怠管理システムの導入:勤務時間の記録と報告を電子化
・残業抑制インセンティブ:残業時間を抑えた社員に報奨金や表彰制度を導入
▶発注者側からの働き方改善の要請
発注者である国や地方自治体、NEXCOやUR都市機構といった機関も、過重労働の是正に積極的に取り組んでいるのが近年の傾向です。
その背景には、建設業界全体の人材不足、若手技術者の離職率の高さ、そして長時間労働による健康被害への懸念があります。
これを受け、発注者は次のような取り組みを強化しています:
・勤務時間のガイドライン提示:派遣職員の労働時間に上限を設ける
・業務分担の見直し:発注者内部の職員と業務の役割を再整理
・ICT化による省力化の推進:電子納品・リモート会議・ペーパーレス化など
これにより、「支援業務=激務・過酷」というかつてのイメージは、少しずつ解消されつつあります。
「働き方改革」は発注者支援業務でも進んでいる?
「働き方改革」という言葉は、民間企業を中心に語られることが多いですが、近年では公共事業の現場においてもその必要性と重要性が強く認識されるようになってきました。
特に、慢性的な人手不足、技術者の高齢化、若年層の業界離れといった課題を背景に、国や自治体、業界団体を中心に働き方の見直しが加速しています。
発注者支援業務は、そうした流れの中で「公共事業に関わる民間側の担い手」として、働き方改革の最前線に立つ存在とも言えるでしょう。
以下では、実際に現場で見られる改革の取り組みについて、具体例を交えて紹介していきます。
特に、慢性的な人手不足、技術者の高齢化、若年層の業界離れといった課題を背景に、国や自治体、業界団体を中心に働き方の見直しが加速しています。
発注者支援業務は、そうした流れの中で「公共事業に関わる民間側の担い手」として、働き方改革の最前線に立つ存在とも言えるでしょう。
以下では、実際に現場で見られる改革の取り組みについて、具体例を交えて紹介していきます。
ICT活用による業務効率化
まず注目すべきは、ICT(情報通信技術)を活用した業務の効率化です。
国土交通省が推進する「i-Construction(アイ・コンストラクション)」の影響を受け、発注者支援業務でも現場作業の省力化と資料作成の簡略化が目に見えるかたちで進んでいます。
▶主な導入技術とその効果
・ドローン測量の導入:従来は数日〜数週間かかっていた地形調査が、ドローンを使えば数時間〜1日で完了するケースも。
安全性の向上に加え、作業人員の削減にもつながっています。
・電子納品の拡大:以前は膨大な紙資料を印刷・製本し、ファイリングして提出するのが当たり前でしたが、
現在はPDFやCADデータでの納品が主流になりつつあります。
これにより、資料作成や印刷業務の時間とコストが大幅に削減されました。
・BIM/CIMの導入:設計段階から施工・維持管理まで、3Dデータで情報を一元管理する仕組みです。
関係者間での設計・工法の確認や変更点の共有がスムーズになり、二度手間や伝達ミスの削減にもつながっています。
▶ICT導入が働き方に与える影響
これらの技術革新は、単に効率化のためだけでなく、労働時間の短縮やストレスの軽減にも寄与しています。
たとえば、これまで「終電間際までかかっていた図面修正」や「検査用資料の準備」が、ICTの導入によって定時退社が可能になったという現場もあります。
国土交通省が推進する「i-Construction(アイ・コンストラクション)」の影響を受け、発注者支援業務でも現場作業の省力化と資料作成の簡略化が目に見えるかたちで進んでいます。
▶主な導入技術とその効果
・ドローン測量の導入:従来は数日〜数週間かかっていた地形調査が、ドローンを使えば数時間〜1日で完了するケースも。
安全性の向上に加え、作業人員の削減にもつながっています。
・電子納品の拡大:以前は膨大な紙資料を印刷・製本し、ファイリングして提出するのが当たり前でしたが、
現在はPDFやCADデータでの納品が主流になりつつあります。
これにより、資料作成や印刷業務の時間とコストが大幅に削減されました。
・BIM/CIMの導入:設計段階から施工・維持管理まで、3Dデータで情報を一元管理する仕組みです。
関係者間での設計・工法の確認や変更点の共有がスムーズになり、二度手間や伝達ミスの削減にもつながっています。
▶ICT導入が働き方に与える影響
これらの技術革新は、単に効率化のためだけでなく、労働時間の短縮やストレスの軽減にも寄与しています。
たとえば、これまで「終電間際までかかっていた図面修正」や「検査用資料の準備」が、ICTの導入によって定時退社が可能になったという現場もあります。
業務分担の見直し
発注者支援業務は大きく分けて「工事監督支援業務」と「資料作成業務」に分類されます。
以前は一人が複数業務を兼任するケースも多く、業務量の偏りや過重労働の原因となっていました。
しかし最近では、それぞれの業務に特化した人材配置が進み、役割分担が明確化されつつあります。
▶具体的な取り組み例
・「現場対応に長けた技術者」を工事監督支援担当に
・「事務処理や積算に強いスタッフ」を資料作成担当に
こうした業務分担により、一人あたりの負荷を抑え、業務の質を高める効果が期待されています。
また、専門性の向上により、「○○さんに任せれば安心」という信頼関係が発注者との間に築かれやすくなる点も大きなメリットです。
▶効果と課題
この取り組みは確実に働きやすさの向上に貢献している一方で、まだすべての企業や現場に浸透しているわけではありません。
特に小規模な現場や人員に余裕がない組織では、依然として「兼任」が当たり前という状況も残っているため、今後の体制整備と人材育成が鍵となります。
以前は一人が複数業務を兼任するケースも多く、業務量の偏りや過重労働の原因となっていました。
しかし最近では、それぞれの業務に特化した人材配置が進み、役割分担が明確化されつつあります。
▶具体的な取り組み例
・「現場対応に長けた技術者」を工事監督支援担当に
・「事務処理や積算に強いスタッフ」を資料作成担当に
こうした業務分担により、一人あたりの負荷を抑え、業務の質を高める効果が期待されています。
また、専門性の向上により、「○○さんに任せれば安心」という信頼関係が発注者との間に築かれやすくなる点も大きなメリットです。
▶効果と課題
この取り組みは確実に働きやすさの向上に貢献している一方で、まだすべての企業や現場に浸透しているわけではありません。
特に小規模な現場や人員に余裕がない組織では、依然として「兼任」が当たり前という状況も残っているため、今後の体制整備と人材育成が鍵となります。
派遣社員の勤務時間管理の徹底
発注者支援業務の多くは、民間企業からの技術者が派遣職員として発注者のもとで勤務する形をとっています。
そのため、発注者(国や自治体)と派遣元企業の契約内容が、働き方に直接的な影響を与えます。
▶契約時に明記される内容の例
・1日の勤務時間(例:8:30〜17:15、休憩1時間)
・残業上限の明示(例:月45時間以内)
・休日・休暇の取得ルール
・時間外労働の許可制運用
こうした取り決めにより、労働時間が可視化され、無理な働き方を抑止する効果があります。
また、発注者自身も「派遣職員の過重労働は自らの管理責任」と認識しており、職場環境の改善や業務負荷の軽減に積極的に関与するケースが増えています。
▶健康とモチベーション維持にもつながる
勤務時間が明確になり、残業が適正に管理されることで、心身の健康維持や仕事への集中力の向上といった効果も期待できます。
特に若手技術者にとっては、働きすぎによる燃え尽きや離職を防ぐ上で、こうしたルールの整備が重要な“安心材料”となっています。
そのため、発注者(国や自治体)と派遣元企業の契約内容が、働き方に直接的な影響を与えます。
▶契約時に明記される内容の例
・1日の勤務時間(例:8:30〜17:15、休憩1時間)
・残業上限の明示(例:月45時間以内)
・休日・休暇の取得ルール
・時間外労働の許可制運用
こうした取り決めにより、労働時間が可視化され、無理な働き方を抑止する効果があります。
また、発注者自身も「派遣職員の過重労働は自らの管理責任」と認識しており、職場環境の改善や業務負荷の軽減に積極的に関与するケースが増えています。
▶健康とモチベーション維持にもつながる
勤務時間が明確になり、残業が適正に管理されることで、心身の健康維持や仕事への集中力の向上といった効果も期待できます。
特に若手技術者にとっては、働きすぎによる燃え尽きや離職を防ぐ上で、こうしたルールの整備が重要な“安心材料”となっています。
ワークライフバランスも実現可能な働き方へ
発注者支援業務は、「激務」と言われることもありますが、実際には働き方や環境によって大きく変わります。
スケジュールの工夫やチーム連携、制度面の整備が進んでいる現場では、無理なく働ける環境づくりが進行中です。
・スケジュール管理の工夫:業務が集中する前にタスクを前倒しで進めることで、残業の抑制につながります。
・良好な現場コミュニケーション:発注者との信頼関係があれば、指示や調整がスムーズに進み、負担軽減につながります。
・柔軟な働き方の導入:時差出勤やリモートワークといった制度も、企業によっては少しずつ導入が進んでいます。
・有給取得を後押しする文化:比較的業務が落ち着く4月〜6月の閑散期などに、まとまった休暇を取得しやすい職場もあります。
このような取り組みが進んでいる企業や現場では、繁忙期以外は家族との時間やプライベートを大切にしながら働くことも可能です。
自分らしい働き方を実現したい方にも、十分に選択肢のある業務領域と言えるでしょう。
スケジュールの工夫やチーム連携、制度面の整備が進んでいる現場では、無理なく働ける環境づくりが進行中です。
・スケジュール管理の工夫:業務が集中する前にタスクを前倒しで進めることで、残業の抑制につながります。
・良好な現場コミュニケーション:発注者との信頼関係があれば、指示や調整がスムーズに進み、負担軽減につながります。
・柔軟な働き方の導入:時差出勤やリモートワークといった制度も、企業によっては少しずつ導入が進んでいます。
・有給取得を後押しする文化:比較的業務が落ち着く4月〜6月の閑散期などに、まとまった休暇を取得しやすい職場もあります。
このような取り組みが進んでいる企業や現場では、繁忙期以外は家族との時間やプライベートを大切にしながら働くことも可能です。
自分らしい働き方を実現したい方にも、十分に選択肢のある業務領域と言えるでしょう。
まとめ
発注者支援業務は、公共事業を円滑に進めるために欠かせない専門職です。
確かに繁忙期は残業も発生しやすく、業務量も多くなりますが、それは計画的にコントロール可能な部分も多く、働き方改革の進展やICT導入により徐々に改善されてきています。
・残業代が適切に支払われる環境
・時期による業務の波がある分、休みも取りやすい
・公共性の高い仕事に携わるやりがい
・キャリア形成の一環としても有望
発注者支援業務は、激務の一面があるのは事実ですが、それを乗り越える魅力と安定性、そして成長の機会がある仕事です。
「自分に合った働き方ができるか?」「専門性を活かせるか?」この問いへの答えを見つけるためにも、まずは正しい情報を知ることから始めてみましょう。
確かに繁忙期は残業も発生しやすく、業務量も多くなりますが、それは計画的にコントロール可能な部分も多く、働き方改革の進展やICT導入により徐々に改善されてきています。
・残業代が適切に支払われる環境
・時期による業務の波がある分、休みも取りやすい
・公共性の高い仕事に携わるやりがい
・キャリア形成の一環としても有望
発注者支援業務は、激務の一面があるのは事実ですが、それを乗り越える魅力と安定性、そして成長の機会がある仕事です。
「自分に合った働き方ができるか?」「専門性を活かせるか?」この問いへの答えを見つけるためにも、まずは正しい情報を知ることから始めてみましょう。