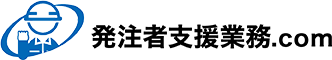建設情報コラム
2025-10-14
施工管理技士の残業時間は月何時間?実態と働きやすい会社の選び方
施工管理技士への転職を検討しているものの、「残業が多い」という噂を聞いて不安に感じていませんか?
確かに施工管理技士の残業時間は一般的な会社員より長い傾向にありますが、会社選びや働き方次第でワークライフバランスを実現することは十分可能です。
この記事では、施工管理技士の平均残業時間や残業が多い理由、そして転職時にチェックすべきポイントまで詳しく解説します。転職後に後悔しないために、ぜひ最後までお読みください。
確かに施工管理技士の残業時間は一般的な会社員より長い傾向にありますが、会社選びや働き方次第でワークライフバランスを実現することは十分可能です。
この記事では、施工管理技士の平均残業時間や残業が多い理由、そして転職時にチェックすべきポイントまで詳しく解説します。転職後に後悔しないために、ぜひ最後までお読みください。
【結論】施工管理技士の残業時間は月30.5時間
転職サイトdodaが2024年に実施した調査によると、施工管理技士の平均残業時間は月30.5時間でした。
一方、同調査における全業種の平均残業時間は月21.0時間、厚生労働省「毎月勤労統計調査(令和6年1月分)」では一般労働者の平均残業時間は月13.2時間となっており、施工管理技士の残業時間は一般的な会社員の約2.3倍という結果になっています。
調査によってバラつきはありますが、施工管理技士の残業時間が一般的な会社員より長いのは事実といえるでしょう。
まずは施工管理技士のアルバイトに挑戦してみたいという方はこちらの記事で詳しく解説していますので、チェックしてみましょう。
一方、同調査における全業種の平均残業時間は月21.0時間、厚生労働省「毎月勤労統計調査(令和6年1月分)」では一般労働者の平均残業時間は月13.2時間となっており、施工管理技士の残業時間は一般的な会社員の約2.3倍という結果になっています。
調査によってバラつきはありますが、施工管理技士の残業時間が一般的な会社員より長いのは事実といえるでしょう。
まずは施工管理技士のアルバイトに挑戦してみたいという方はこちらの記事で詳しく解説していますので、チェックしてみましょう。
職種別の残業時間を比較
建設業界の中でも職種によって残業時間には差があります。以下の表で比較してみましょう。
表:職種別平均残業時間の比較(2024年版)
表:職種別平均残業時間の比較(2024年版)
| 職種 | 平均残業時間/月 |
|---|---|
| 施工管理 | 30.5時間 |
| 設計監理・コンストラクションマネジメント | 31.6時間 |
| 建築設計 | 24.5時間 |
| 建築・土木系エンジニア全体 | 26.0時間 |
| プラントエンジニア | 25.9時間 |
| 設備保全・保守 | 21.9時間 |
| 全業種平均 | 21.0時間 |
※出典:doda「平均残業時間ランキング(2024年版)」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成
この表から、施工管理の残業時間は建設業界の中でも比較的多いことが分かります。ただし、設計監理職も同程度の残業時間であり、業界全体として現場管理系の職種は残業が多い傾向にあるといえるでしょう。
また注目すべき点は、2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用された影響で、設計監理職は前年比マイナス7.5時間、建築設計職はマイナス6.6時間と大幅に減少していることです。
今後、施工管理職でも同様の改善が期待されます。
施工管理技士の残業時間が多い5つの理由
施工管理技士の残業時間が一般的な会社員より長くなる背景には、いくつかの構造的な理由があります。
ここでは主な5つの理由を解説していきます。
ここでは主な5つの理由を解説していきます。
1.業務量が多く、現場と事務作業を両立する必要がある
施工管理技士の業務は現場管理だけではありません。
日中は現場での工程管理、安全管理、品質管理に追われ、現場作業が終わる夕方以降に事務作業に取り組むことになります。
具体的には、以下のような事務作業が発生するでしょう。
日中は現場での工程管理、安全管理、品質管理に追われ、現場作業が終わる夕方以降に事務作業に取り組むことになります。
具体的には、以下のような事務作業が発生するでしょう。
- 工事写真の整理
- 図面の作成・修正
- 打ち合わせ資料の作成
- 工程表の更新
- 原価計算
- 発注書類や請求書の作成
- 報告書の作成
これらの事務作業は集中力を要するため、現場作業が終わった後にまとまった時間を確保する必要があり、結果として残業が発生しやすくなります。
施工管理技士の仕事内容については、こちらの記事を確認してみましょう。
技術士との違いも詳しく解説しています。
施工管理技士の仕事内容については、こちらの記事を確認してみましょう。
技術士との違いも詳しく解説しています。
2.深刻な人手不足で一人当たりの負担が大きい
建設業界全体が高齢化しており、若手の入職者が少ないことが深刻な問題となっています。
特に施工管理技士は国家資格が必要なため、有資格者の確保が難しい状況です。
企業によっては施工管理技士が数名しかいないケースもあり、少数の有資格者に業務が集中しています。
本来であれば複数人で分担すべき業務を一人で抱え込むことになり、労働時間が長くなる要因となっているのです。
特に施工管理技士は国家資格が必要なため、有資格者の確保が難しい状況です。
企業によっては施工管理技士が数名しかいないケースもあり、少数の有資格者に業務が集中しています。
本来であれば複数人で分担すべき業務を一人で抱え込むことになり、労働時間が長くなる要因となっているのです。
3.工期の厳守が絶対で、スケジュール調整が難しい
建設工事では施主との約束である工期を厳守することが求められますが、現場では予期せぬトラブルが頻繁に発生します。
【想定されるトラブルの例】
【想定されるトラブルの例】
- 天候不良による工事の遅延
- 資材の納品遅れ
- 設計変更の発生
- 前工程の遅れによる影響
- 予期せぬ地盤や構造物の問題
これらのトラブルが発生しても工期を延ばすことは容易ではないため、遅れを取り戻すために残業や休日出勤で対応せざるを得ない可能性があります。
特に下請けの立場では、元請けや次の工程への影響を考慮して無理をしてでも工期内に収める必要があります。
特に下請けの立場では、元請けや次の工程への影響を考慮して無理をしてでも工期内に収める必要があります。
4.業界全体で「長時間労働が当たり前」の風潮が残っている
建設業界は古くからの体質が残っており、「残業や休日出勤は当たり前」という風潮がまだ根強く存在します。
特にベテラン世代にこの傾向が強く、若手もその影響を受けやすい環境です。
また、施工管理技士は現場の責任者として、作業の開始から終了まで現場にいることが求められる立場にあります。
作業員が残業する場合は一緒に残らなければならず、自分の判断だけで退社時間をコントロールできないケースも少なくありません。
特にベテラン世代にこの傾向が強く、若手もその影響を受けやすい環境です。
また、施工管理技士は現場の責任者として、作業の開始から終了まで現場にいることが求められる立場にあります。
作業員が残業する場合は一緒に残らなければならず、自分の判断だけで退社時間をコントロールできないケースも少なくありません。
5.会社の労務管理体制が整っていない
企業によって労務管理の体制には大きな差があり、これが残業時間に直結しています。
労務管理体制が不十分な企業では、以下のような問題が見られるでしょう。
労務管理体制が不十分な企業では、以下のような問題が見られるでしょう。
- DX化が進んでおらず、手作業での事務処理が多い
- 適正な工期設定ができていない
- 人員配置の最適化がされていない
- 残業時間の管理が甘く、長時間労働が常態化している
- 業務効率化のための投資が不足している
一方、DX化や業務効率化に積極的に取り組んでいる企業では、同じ施工管理の仕事でも残業時間を大幅に削減できている事例があります。
つまり、残業時間は会社の取り組み次第で改善できる余地が大きいのです。
つまり、残業時間は会社の取り組み次第で改善できる余地が大きいのです。
施工管理技士の残業時間は会社によって大きく変わる
同じ施工管理技士という職種でも、所属する会社や業種によって残業時間には大きな差があります。
転職を検討する際は、この点を十分に理解しておくことが重要です。
施工管理技士の種類についてはこちらの記事を確認してみましょう。
転職を検討する際は、この点を十分に理解しておくことが重要です。
施工管理技士の種類についてはこちらの記事を確認してみましょう。
大手ゼネコンと中小企業の違い
企業規模によって労働環境には明確な違いがあります。以下の表で比較してみましょう。
表:企業規模別の特徴比較
表:企業規模別の特徴比較
| 項目 | 大手ゼネコン | 中小建設会社 |
|---|---|---|
| 業務分担 | 分業体制が整っており、一人当たりの業務範囲が明確 | 一人で複数の役割を担当するため、業務範囲が広くなりがち |
| 労務管理 | 残業時間の上限管理が厳格に徹底されている | 労務管理の体制が整っていない企業も存在する |
| DX化・業務効率化 | 投資が進んでおり、業務効率化ツールが充実 | 投資が限られ、アナログな業務が残っているケースも |
| 残業時間の傾向 | 平均的には管理されているが、大型案件担当時は繁忙期の残業が増える可能性あり | 案件規模が小さいため、柔軟な働き方ができるケースもある一方、人手不足で長時間化することも |
一概にどちらが良いとは言えませんが、残業時間を重視するのであれば、労務管理体制が整った企業を選ぶことが重要でしょう。
業種による施工管理技士の残業時間の差
施工管理の仕事でも、業種や分野によって残業時間には差があります。
以下の表で業種別の傾向を確認してみましょう。
表:業種別の平均残業時間の傾向
以下の表で業種別の傾向を確認してみましょう。
表:業種別の平均残業時間の傾向
| 業種 | 残業時間の傾向 | 特徴 |
|---|---|---|
| 大手ゼネコン(新築) | 多い(月50〜60時間程度) | 大型案件が多く、工期も厳しい |
| ハウスメーカー | やや多い(月40〜50時間程度) | 繁忙期と閑散期の差が大きい |
| 不動産管理・修繕 | 比較的少ない(月35〜40時間程度) | 改修工事がメインで工期に余裕あり |
| リノベーション専門 | 比較的少ない(月30〜35時間程度) | 小規模案件が多く、スケジュール調整しやすい |
| 設備メンテナンス | 少ない(月25〜30時間程度) | 定期点検業務が中心で予定が立てやすい |
※上記は一般的な傾向であり、企業によって実態は異なります
この表から分かるように、新築の大型案件を手がける企業ほど残業時間が多くなる傾向があります。
一方、改修工事やメンテナンス業務を中心とする企業では、比較的残業時間を抑えられる可能性が高いでしょう。
転職先を選ぶ際は、「施工管理技士」という職種だけでなく、どの業種・分野の企業なのかまで考慮することをおすすめします。
働き方改革に積極的な企業の特徴
施工管理技士の残業時間を削減している企業には、いくつかの共通点があります。
【残業削減に成功している企業の特徴】
【残業削減に成功している企業の特徴】
- DX化への積極投資:施工管理アプリ、遠隔臨場システム、クラウド型工程管理ツールなどを導入
- 36協定の厳格な遵守:残業時間の上限を明確に管理し、超過しないよう体制を整備
- 週休2日制の実施:完全週休2日または週休2日制(月8日以上)を実現
- 適正工期の設定:無理な工期設定を避け、施主と十分に協議して余裕を持った計画を立案
- 人員配置の最適化:適切な人数の施工管理技士を配置し、負担を分散
求人票や面接でこれらのポイントを確認することで、働きやすい環境の企業を見分けることができます。
【2024年4月〜】施工管理技士の残業時間は働き方改革で改善されていく
2024年4月から建設業にも労働基準法に基づく時間外労働の上限規制が適用され、業界全体で大きな転換期を迎えています。
36協定の上限規制が建設業にも適用
2019年の労働基準法改正により、多くの業界で時間外労働の上限規制が導入されましたが、建設業には5年間の猶予期間が設けられていました。
この猶予期間が2024年3月末で終了し、4月からは建設業にも以下の規制が適用されています。
この猶予期間が2024年3月末で終了し、4月からは建設業にも以下の規制が適用されています。
| 協定の種類 | 残業時間の上限 |
|---|---|
| 通常の36協定 | 月45時間以内、年360時間以内 |
| 特別条項付き36協定 | 年720時間以内、月100時間未満(休日労働含む)、2〜6ヶ月平均で月80時間以内 |
※災害復旧・復興事業を除く
これらの規制に違反した企業には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、悪質な違反が認められた場合は、厚生労働省から企業名が公表されることもあり、企業のブランディングにも大きな影響を及ぼすでしょう。
今後期待される労働環境の変化
働き方改革の推進により、以下のような改善が期待されています。
【期待される変化のポイント】
【期待される変化のポイント】
- 週休2日制の普及:国土交通省の「建設業働き方改革加速化プログラム」でも週休2日制の導入が推進されており、完全週休2日を実現する企業が増加
- 適正工期の設定推進:改正建設業法では、著しく短い工期での請負契約が禁止され、適正な工期設定が法的に求められるように
- DX化による業務効率化:AI、ICT、IoTなどのデジタル技術を活用した省人化・高速化、事務処理の効率化が加速
- 若手人材の流入:労働環境の改善により業界のイメージが向上し、若手の入職者増加が見込まれる
実際に、dodaの調査データでも建設業の残業時間は減少傾向にあり、働き方改革の効果が表れつつあります。
今後さらにこの流れが加速していくことが期待されるでしょう。
施工管理技士1級を取得してキャリアアップを目指したい方はこちらの記事で詳しく解説しています。
今後さらにこの流れが加速していくことが期待されるでしょう。
施工管理技士1級を取得してキャリアアップを目指したい方はこちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ|施工管理技士の残業時間は会社選びで大きく変わる
施工管理技士の平均残業時間は月30.5時間と、一般的な会社員より多いのが現状です。業務量の多さ、人手不足、工期の厳しさなど、複数の要因が重なって残業が発生しやすい構造になっています。
しかし、同じ施工管理技士という職種でも、会社の規模や業種、労務管理体制によって残業時間には大きな差があることも事実です。
大手企業や働き方改革に積極的な企業では、DX化や業務効率化により残業時間を大幅に削減している事例もあります。
2024年4月から建設業にも36協定の上限規制が適用され、業界全体で労働環境の改善が進んでいます。実際にdodaの調査データでも、建設関連職種の残業時間は減少傾向にあり、今後さらなる改善が期待できるでしょう。
転職を検討する際は、残業時間だけでなく、年収、キャリアパス、やりがい、将来性など、総合的に判断することが重要です。
求人票の確認、面接での質問、転職口コミサイトの活用など、複数の方法で情報を集め、自分に合った企業を見つけてください。
不安や疑問がある場合は、建設業界専門の転職エージェントに相談することをおすすめします。
求人票に載らない詳細な労働環境の情報や、企業の内部事情まで教えてもらえるため、転職活動をより効率的に進められるはずです。
施工管理技士は専門性が高く、将来性のある魅力的な職種です。
適切な会社選びをすることで、やりがいを持ちながらワークライフバランスも実現できる働き方が可能になります。
しかし、同じ施工管理技士という職種でも、会社の規模や業種、労務管理体制によって残業時間には大きな差があることも事実です。
大手企業や働き方改革に積極的な企業では、DX化や業務効率化により残業時間を大幅に削減している事例もあります。
2024年4月から建設業にも36協定の上限規制が適用され、業界全体で労働環境の改善が進んでいます。実際にdodaの調査データでも、建設関連職種の残業時間は減少傾向にあり、今後さらなる改善が期待できるでしょう。
転職を検討する際は、残業時間だけでなく、年収、キャリアパス、やりがい、将来性など、総合的に判断することが重要です。
求人票の確認、面接での質問、転職口コミサイトの活用など、複数の方法で情報を集め、自分に合った企業を見つけてください。
不安や疑問がある場合は、建設業界専門の転職エージェントに相談することをおすすめします。
求人票に載らない詳細な労働環境の情報や、企業の内部事情まで教えてもらえるため、転職活動をより効率的に進められるはずです。
施工管理技士は専門性が高く、将来性のある魅力的な職種です。
適切な会社選びをすることで、やりがいを持ちながらワークライフバランスも実現できる働き方が可能になります。
参考文献・データ出典
本記事は以下の信頼できる情報源を参考に作成しています。
【統計データ】
doda「平均残業時間の実態調査(2024年版)」
調査期間:2024年4〜6月、実施:2024年8月
https://doda.jp/guide/zangyo/
厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年1月分結果速報」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r06/2401p/2401p.html
【法令・制度】
厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
【統計データ】
doda「平均残業時間の実態調査(2024年版)」
調査期間:2024年4〜6月、実施:2024年8月
https://doda.jp/guide/zangyo/
厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年1月分結果速報」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r06/2401p/2401p.html
【法令・制度】
厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
施工管理技士に転職するなら!
求人情報を要チェック!
\\求人情報は毎日更新中//