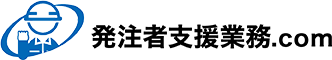2025-10-17建設情報コラム
1級土木施工管理技士の難易度は?合格率・勉強時間から見る取得戦略
転職でキャリアアップを目指すなら、1級土木施工管理技士の資格取得は有力な選択肢です。
しかし、合格率や必要な勉強時間を見ると「今の仕事を続けながら取得できるのか」「転職前に取るべきか、転職後に取るべきか」と悩む方も多いでしょう。
本記事では、1級土木施工管理技士の難易度を数字で示しながら、転職を成功させるための資格取得戦略を解説します。
しかし、合格率や必要な勉強時間を見ると「今の仕事を続けながら取得できるのか」「転職前に取るべきか、転職後に取るべきか」と悩む方も多いでしょう。
本記事では、1級土木施工管理技士の難易度を数字で示しながら、転職を成功させるための資格取得戦略を解説します。
1級土木施工管理技士の難易度を数字で見る
1級土木施工管理技士の難易度を判断するには、合格率、必要な勉強時間、他資格との比較が重要です。
ここでは客観的なデータをもとに、資格取得の難易度を具体的に解説します。
1級土木施工管理技士の合格ラインについてはこちらの記事を参考にしてください。
ここでは客観的なデータをもとに、資格取得の難易度を具体的に解説します。
1級土木施工管理技士の合格ラインについてはこちらの記事を参考にしてください。
合格率の推移と傾向
1級土木施工管理技士の合格率は、一次検定と二次検定で大きく異なります。
近年の合格率は以下の通りです。
近年の合格率は以下の通りです。
| 年度 | 一次検定合格率 | 二次検定合格率 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 44.4% | 41.2% |
| 2023年度 | 49.5% | 33.2% |
| 2022年度 | 54.6% | 28.7% |
| 2021年度 | 60.6% | 36.6% |
| 2020年度 | 60.1% | 31.0% |
一次検定の合格率は44〜60%で推移していますが、2024年度は制度変更の影響で44.4%と過去10年間で最も低い数値を記録しました。
一方、二次検定の合格率は約30〜40%と、一次検定よりも大幅に低くなっています。
この合格率から分かる通り、一次検定は約半数が合格できる水準ですが、二次検定は3人に1人程度しか合格できない狭き門です。
両方に合格して初めて1級土木施工管理技士を名乗れるため、最終的な合格率はさらに低くなります。
合格に必要な勉強時間
資格取得に必要な勉強時間は、1級と2級で異なります。
【勉強時間の目安】
【勉強時間の目安】
- 1級土木施工管理技士:500〜600時間
- 2級土木施工管理技士:300〜400時間
1級の場合、1日2時間のペースで勉強を進めたとしても、250〜300日間(約8〜10ヶ月)が必要です。
試験は年1回しか実施されないため、長期的な学習計画が求められます。
働きながら勉強する場合、残業や現場の繁忙期を考慮すると、さらに時間がかかる可能性も高いでしょう。
平日に2時間を確保するのが難しい場合は、休日に集中して学習時間を取る必要があります。
このように、1級土木施工管理技士は「片手間で取れる資格」ではありません。
計画的に時間を確保できるかどうかが、合格の鍵を握ります。
試験は年1回しか実施されないため、長期的な学習計画が求められます。
働きながら勉強する場合、残業や現場の繁忙期を考慮すると、さらに時間がかかる可能性も高いでしょう。
平日に2時間を確保するのが難しい場合は、休日に集中して学習時間を取る必要があります。
このように、1級土木施工管理技士は「片手間で取れる資格」ではありません。
計画的に時間を確保できるかどうかが、合格の鍵を握ります。
他の施工管理技士資格との比較
土木施工管理技士は、他の施工管理技士資格と比較してどの程度の難易度なのでしょうか。
以下は1級資格の一次検定合格率の比較です。
以下は1級資格の一次検定合格率の比較です。
| 資格名 | 2023年度合格率 | 2022年度合格率 |
|---|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 49.5% | 54.6% |
| 1級建築施工管理技士 | 41.6% | 46.8% |
| 1級管工事施工管理技士 | 37.5% | 42.9% |
この比較から、土木施工管理技士は施工管理技士系の資格の中では比較的合格率が高い傾向にあることが分かります。
ただし、これは「簡単」という意味ではありません。
受験資格として実務経験が必要なため、受験者のレベルが一定以上であることが前提です。
他資格と比較して合格率が高めとはいえ、約半数は不合格になる試験であることを忘れてはいけません。
1級土木施工管理技士試験の難易度を決める3つの要素
合格率だけでは測れない難易度があります。
試験範囲の広さ、記述式問題への対応、実務経験の記述など、1級土木施工管理技士特有の難しさを理解しておきましょう。
試験範囲の広さ、記述式問題への対応、実務経験の記述など、1級土木施工管理技士特有の難しさを理解しておきましょう。
幅広い試験範囲への対応
1級土木施工管理技士の一次検定では、以下の3分野から出題されます。
【出題分野】
【出題分野】
- 土木工学等:土木工学、電気工学、機械工学、建築学などの一般知識
- 施工管理法:施工計画、工程管理、品質管理、安全管理に関する知識と応用能力
- 法規:建設工事の施工管理に必要な法令知識
一次検定は全96問中65問を選択して解答する形式です。幅広い分野から出題されるため、苦手分野を作らないバランスの良い学習が求められます。
特に施工管理法は、全体で60%以上の得点に加えて、施工管理法単独でも60%以上の得点が必要という厳しい合格基準が設けられています。
この分野を重点的に対策することが合格への近道です。
特に施工管理法は、全体で60%以上の得点に加えて、施工管理法単独でも60%以上の得点が必要という厳しい合格基準が設けられています。
この分野を重点的に対策することが合格への近道です。
二次検定の記述問題が高いハードル
一次検定がマークシート方式であるのに対し、二次検定は記述式です。この形式の違いが、合格率の差に大きく影響しています。
記述式問題では、知識を暗記しているだけでは不十分です。以下のスキルが求められます。
記述式問題では、知識を暗記しているだけでは不十分です。以下のスキルが求められます。
- 専門用語を正確に使いこなす能力
- 論理的に文章を構成する力
- 簡潔かつ的確に要点をまとめる力
マークシート方式に慣れている方にとって、記述式への切り替えは想像以上に難しいものです。
普段から文章を書く習慣がない場合、この部分に多くの時間を割く必要があるでしょう。
二次検定の合格率が30〜40%と低いのは、この記述問題への対応が不十分な受験者が多いことも一因です。
普段から文章を書く習慣がない場合、この部分に多くの時間を割く必要があるでしょう。
二次検定の合格率が30〜40%と低いのは、この記述問題への対応が不十分な受験者が多いことも一因です。
経験記述問題の対策の難しさ
二次検定で最も対策が難しいのが、経験記述問題です。
経験記述問題とは、自分が実際に携わった工事について、技術的な課題や実施した対策を記述する問題のこと。この問題は配点が高く、合否を分ける重要なポイントとなります。
経験記述問題が難しい理由は以下の通りです。
経験記述問題とは、自分が実際に携わった工事について、技術的な課題や実施した対策を記述する問題のこと。この問題は配点が高く、合否を分ける重要なポイントとなります。
経験記述問題が難しい理由は以下の通りです。
- 自分の実務経験を客観的に整理する必要がある
- テーマに沿って適切な工事を選定しなければならない
- 模範解答の丸暗記では実体験が伝わらず減点される
- 短期間での対策では文章の完成度が低くなる
過去問や問題集を使って、何度も書き直す練習が必要です。
できれば試験の数ヶ月前から準備を始めることをおすすめします。
できれば試験の数ヶ月前から準備を始めることをおすすめします。
転職市場における1級土木施工管理技士の価値
資格取得の労力に見合う価値があるのか、転職を考える上で重要なポイントです。
年収、求人需要、そして地域や企業規模による価値の違いを把握しましょう。
施工管理技士の働き方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
年収、求人需要、そして地域や企業規模による価値の違いを把握しましょう。
施工管理技士の働き方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
資格取得による年収への影響
厚生労働省の職業情報提供サイトによると、土木施工管理技士の平均年収は約604万円とされています。
ただし、このデータには1級と2級の両方が含まれているため、1級保有者に限定すればさらに高い水準になるでしょう。
資格取得による年収への影響は以下の通りです。
【年収アップの要素】
ただし、このデータには1級と2級の両方が含まれているため、1級保有者に限定すればさらに高い水準になるでしょう。
資格取得による年収への影響は以下の通りです。
【年収アップの要素】
- 資格手当:月1〜3万円程度(年間12〜36万円)
- 昇進・昇格:監理技術者として責任あるポジションに就ける
- 大規模工事への参画:プロジェクト規模が大きくなることで給与水準も上昇
- 転職時の交渉力:好条件での採用が期待できる
実際、年収1,000万円を超える土木施工管理技士も一定数存在します。
経験を積み、大規模プロジェクトの責任者として活躍できれば、高収入を実現することも可能です。
少子高齢化による人手不足が深刻化する中、1級土木施工管理技士の市場価値は今後さらに高まると予想されます。
経験を積み、大規模プロジェクトの責任者として活躍できれば、高収入を実現することも可能です。
少子高齢化による人手不足が深刻化する中、1級土木施工管理技士の市場価値は今後さらに高まると予想されます。
求人市場での需要と引く手あまたの実態
1級土木施工管理技士は、転職市場で非常に高く評価される資格です。
その理由は以下の通りです。
【高く評価される理由】
その理由は以下の通りです。
【高く評価される理由】
- 大規模工事の監理技術者になれる:請負金額の制限なく現場管理者として従事可能
- 企業の入札要件を満たす:公共工事の入札で有利になる技術者として位置づけられる
- 深刻な人手不足:建設業界全体で有資格者が不足しており需要が高い
特に事業拡大を目指す企業では、1級資格者の採用に積極的です。
好条件での転職オファーを受けることも珍しくありません。
ただし、「引く手あまた」の状態を実現するには、資格だけでなく実務経験も重要です。
資格と経験の両方を兼ね備えた人材が、最も市場価値が高いと言えるでしょう。
好条件での転職オファーを受けることも珍しくありません。
ただし、「引く手あまた」の状態を実現するには、資格だけでなく実務経験も重要です。
資格と経験の両方を兼ね備えた人材が、最も市場価値が高いと言えるでしょう。
地域・企業規模による資格の重要度の違い
1級土木施工管理技士の価値は、働く地域や企業規模によって異なります。
| 比較項目 | 都市部 | 地方 |
|---|---|---|
| 求人数 | 多い | 少ない |
| 年収水準 | 高め | 低め |
| 競争率 | 高い | 低い |
都市部では求人数が多く年収水準も高い傾向にありますが、有資格者も多いため競争は激しくなります。
一方、地方では求人数は少ないものの、有資格者が不足しているため貴重な存在として重宝されるでしょう。
企業規模による違いも重要です。
【大手ゼネコン】
- 1級資格は「持っていて当たり前」の水準
- 資格よりも実績やマネジメント能力が重視される傾向
- 年収水準は高いが、競争も激しい
【中小企業・地域密着型企業】
- 1級資格保有者が少なく、高く評価される
- 即座に監理技術者として活躍できる
- 公共工事の受注拡大に貢献できる人材として歓迎される
転職先を選ぶ際は、自分のキャリアプランと資格の活かし方を考慮することが大切です。
大規模プロジェクトに挑戦したいなら大手を、地域に根ざして働きたいなら中小企業を検討するとよいでしょう。
大規模プロジェクトに挑戦したいなら大手を、地域に根ざして働きたいなら中小企業を検討するとよいでしょう。
資格取得タイミング別の転職戦略
転職前に取るべきか、転職後に取るべきか。
この判断が転職の成否を分けます。
それぞれのメリット・デメリット、さらに一次試験のみ合格の状態での転職可能性まで、具体的な戦略を解説します。
1級土木施工管理技士のメリットについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
この判断が転職の成否を分けます。
それぞれのメリット・デメリット、さらに一次試験のみ合格の状態での転職可能性まで、具体的な戦略を解説します。
1級土木施工管理技士のメリットについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
転職前に資格を取得する場合
現在の会社に在籍しながら資格を取得し、その後転職するパターンです。
【メリット】
【メリット】
- 好条件での転職交渉が可能になる
- 求人の選択肢が大幅に広がる
- 即戦力として高く評価される
- 資格手当がある企業へ確実に転職できる
【デメリット】
- 現職が忙しく勉強時間の確保が困難
- 不合格の場合、転職タイミングが遅れる
- 会社の資格取得支援制度を受けられない可能性がある
- 500〜600時間の勉強期間(8〜10ヶ月)を要する
このパターンが向いているのは、以下のような方です。
1.現職に比較的余裕があり、勉強時間を確保できる
2.確実に好条件で転職したい
3.不合格でも現職を続けられる環境にある
4.すでに2級を保有しており、ステップアップを目指している
1.現職に比較的余裕があり、勉強時間を確保できる
2.確実に好条件で転職したい
3.不合格でも現職を続けられる環境にある
4.すでに2級を保有しており、ステップアップを目指している
転職前の資格取得は、交渉力を最大化できる最も理想的なパターンです。
ただし、不合格のリスクも考慮し、「資格が取れなくても転職できる実力」を持っておくことが重要でしょう。
ただし、不合格のリスクも考慮し、「資格が取れなくても転職できる実力」を持っておくことが重要でしょう。
転職後に資格を取得する場合
資格を持たない状態で転職し、転職先で資格取得を目指すパターンです。
【メリット】
【メリット】
- 資格取得支援制度がある企業を選べる
- 勉強に専念できる環境を確保しやすい
- 実務経験を積みながら学べる
- 今すぐ転職できる
【デメリット】
- 転職時の交渉力が弱い
- 資格なしでの採用条件になり、初任給が低い可能性
- 資格取得後に一定期間勤務する「縛り」がある場合も
- 会社から取得を求められるプレッシャーがある
このパターンが向いているのは、以下のような方です。
1.今すぐ転職したい事情がある
2.2級を保有しており、実務経験が豊富
3.資格支援が充実した企業に転職できる見込みがある
4.現職の環境が悪く、早期に脱出したい
1.今すぐ転職したい事情がある
2.2級を保有しており、実務経験が豊富
3.資格支援が充実した企業に転職できる見込みがある
4.現職の環境が悪く、早期に脱出したい
「資格取得支援制度あり」の求人を探す際は、支援内容の詳細を確認しましょう。
受験費用の負担だけなのか、勉強時間の確保や講習会への参加もサポートしてくれるのか、企業によって大きく異なります。
受験費用の負担だけなのか、勉強時間の確保や講習会への参加もサポートしてくれるのか、企業によって大きく異なります。
一次試験合格(技士補)での転職の可能性
2024年度の制度変更により、一次検定に合格すると「技士補」の資格が付与されるようになりました。
技士補の位置づけは以下の通りです。
【技士補でできること】
技士補の位置づけは以下の通りです。
【技士補でできること】
- 監理技術者補佐として勤務可能
- 一次検定合格の有効期限が無期限に
- 一定の専門知識を持つ証明になる
技士補の状態で転職する場合、市場価値は「無資格者よりは高いが、1級保有者には及ばない」という評価になります。
ただし、以下のようなアピールができるでしょう。
ただし、以下のようなアピールができるでしょう。
- 「1級土木施工管理技士を目指して学習中」と前向きな姿勢を示せる
- 二次試験に向けて継続的に努力していることを証明できる
- 入社後、早期に1級を取得できる見込みがあることを伝えられる
一次試験合格後すぐに転職活動を始めるか、二次試験の結果を待つかは、以下の要素で判断しましょう。
| 判断基準 | すぐ転職活動 | 二次試験後に転職活動 |
|---|---|---|
| 現職の状況 | 早急に環境を変えたい | 今の環境でもう少し我慢できる |
| 二次試験の手応え | 自信がない | 合格の可能性が高い |
| 転職市場の状況 | 好条件の求人が出ている | 特に急いでいない |
技士補の状態でも、実務経験が豊富であれば十分に転職は可能です。
二次試験の勉強と転職活動を並行して進めることもできますが、両立が難しい場合はどちらかに集中する決断も必要でしょう。
1級土木施工管理技士を働きながら取得するための効率的な学習方法
500〜600時間の勉強時間を、働きながらどう確保するか。
転職を考えている忙しい方でも実践できる、効率的な学習方法と時間管理のコツを紹介します。
1級土木施工管理技士の効率的な勉強方法について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてみましょう。
転職を考えている忙しい方でも実践できる、効率的な学習方法と時間管理のコツを紹介します。
1級土木施工管理技士の効率的な勉強方法について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてみましょう。
逆算式の学習計画の立て方
合格するために最も重要なのは、計画性です。
試験日から逆算してスケジュールを立てましょう。
【学習計画の立て方】
試験日から逆算してスケジュールを立てましょう。
【学習計画の立て方】
- 試験日を確認:1級は年1回(例年7月)
- 必要な勉強時間を算出:500〜600時間
- 1日の勉強時間を決定:平日2時間、休日4時間など
- 一次・二次の対策期間を分割:一次300時間、二次200〜300時間
- 余裕を持たせる:仕事の繁忙期を考慮し、予備日を設ける
1日2時間を確保する場合、8〜10ヶ月前から学習を開始する必要があります。
試験は年1回しかないため、「今年は無理だから来年」という選択肢は、1年のブランクを意味することを忘れないでください。
一次検定と二次検定の対策は並行して進めるのではなく、まず一次に集中し、合格後に二次対策に移るのが効率的です。
試験は年1回しかないため、「今年は無理だから来年」という選択肢は、1年のブランクを意味することを忘れないでください。
一次検定と二次検定の対策は並行して進めるのではなく、まず一次に集中し、合格後に二次対策に移るのが効率的です。
働きながら勉強時間を確保する具体策
建設業界は残業が多く、勉強時間の確保が最大の課題です。以下の具体策を実践しましょう。
【時間確保の工夫】
【時間確保の工夫】
- 通勤時間の活用:スマホアプリで過去問演習や暗記学習
- 早朝学習:出勤前の1時間を勉強に充てる(頭が冴えている)
- 昼休みの活用:15分でも積み重ねれば大きな差になる
- 休日の計画的な学習:午前中に3〜4時間集中する
特に有効なのは早朝学習です。仕事で疲れた夜よりも、朝の方が集中力が高く、効率的に学習できます。
「1日最低2時間」をルールとして決め、毎日継続することが合格への近道です。
繁忙期と試験時期が重なる場合は、事前に上司に相談し、できるだけ負担を軽減してもらうことも検討しましょう。
会社によっては、資格取得を応援してくれる体制が整っている場合もあります。
「1日最低2時間」をルールとして決め、毎日継続することが合格への近道です。
繁忙期と試験時期が重なる場合は、事前に上司に相談し、できるだけ負担を軽減してもらうことも検討しましょう。
会社によっては、資格取得を応援してくれる体制が整っている場合もあります。
まとめ:1級土木施工管理技士は難易度の高い試験
1級土木施工管理技士の難易度は、一次検定の合格率約50%、二次検定約30〜40%という数字が示す通り、決して簡単ではありません。
500〜600時間の勉強時間が必要で、特に二次検定の記述問題と経験記述が高いハードルとなります。
しかし、転職市場では高く評価され、年収アップや大規模プロジェクトへの参画が可能になるなど、取得する価値は十分にあります。
重要なのは資格取得のタイミングです。
現職で余裕があり好条件での転職を目指すなら転職前の取得を、今すぐ環境を変えたいなら資格支援が充実した企業への転職後の取得を検討しましょう。
一次試験合格(技士補)の状態でも、転職市場では一定の評価を得られます。
自分のキャリアプランと現在の状況を踏まえて、最適な戦略を選択してください。
500〜600時間の勉強時間が必要で、特に二次検定の記述問題と経験記述が高いハードルとなります。
しかし、転職市場では高く評価され、年収アップや大規模プロジェクトへの参画が可能になるなど、取得する価値は十分にあります。
重要なのは資格取得のタイミングです。
現職で余裕があり好条件での転職を目指すなら転職前の取得を、今すぐ環境を変えたいなら資格支援が充実した企業への転職後の取得を検討しましょう。
一次試験合格(技士補)の状態でも、転職市場では一定の評価を得られます。
自分のキャリアプランと現在の状況を踏まえて、最適な戦略を選択してください。
1級土木施工管理技士の資格で今すぐ活躍したい方は!
求人情報を要チェック!
\\求人情報は毎日更新中//