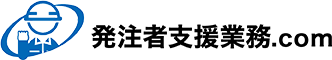2025-10-27建設情報コラム
施工管理から「家族との時間」を取り戻す転職|発注者支援という選択
「また今日も日付が変わってしまった」「子どもの寝顔しか見られていない」
—そんな風に感じている、現場の施工管理技術者の方は少なくないでしょう。
長年にわたり、日本の建設業界は長時間労働が常態化してきたという歴史を持っています。実際、全産業と比較して、建設業の年間出勤日数は12日も多く、年間総実労働時間は68時間も長いというデータが示されています(令和4年度)。さらに、多くの技術者が、他産業では当たり前の4週8休(週休2日)の確保ができておらず、「4週6休程度」が最多となっているのが現状なのです。
特に、家庭を持つ30代から40代の技術者にとって、この過酷な労働環境は深刻な二者択一を迫ります。それは「キャリアを継続して家族を養うか」、それとも「私生活を優先して働く環境を変えるか」という重い選択です。
しかし、2024年4月から建設業にも適用された時間外労働の上限規制(2024年問題)は、業界全体に働き方改革を義務付け、技術者がキャリアを見直す大きな転機となっています。
本記事では、この変化を前向きな機会として捉え、施工管理の経験を活かしつつ、「家族との時間」を取り戻すための具体的な道筋として、発注者支援業務へのキャリアチェンジを提案します。年収を維持・向上させながら、なぜ発注者支援業務がワークライフバランス(WLB)を実現しやすいのか、その具体的な理由と、あなたの技術的価値を維持・向上させる方法を解説していきましょう。
—そんな風に感じている、現場の施工管理技術者の方は少なくないでしょう。
長年にわたり、日本の建設業界は長時間労働が常態化してきたという歴史を持っています。実際、全産業と比較して、建設業の年間出勤日数は12日も多く、年間総実労働時間は68時間も長いというデータが示されています(令和4年度)。さらに、多くの技術者が、他産業では当たり前の4週8休(週休2日)の確保ができておらず、「4週6休程度」が最多となっているのが現状なのです。
特に、家庭を持つ30代から40代の技術者にとって、この過酷な労働環境は深刻な二者択一を迫ります。それは「キャリアを継続して家族を養うか」、それとも「私生活を優先して働く環境を変えるか」という重い選択です。
しかし、2024年4月から建設業にも適用された時間外労働の上限規制(2024年問題)は、業界全体に働き方改革を義務付け、技術者がキャリアを見直す大きな転機となっています。
本記事では、この変化を前向きな機会として捉え、施工管理の経験を活かしつつ、「家族との時間」を取り戻すための具体的な道筋として、発注者支援業務へのキャリアチェンジを提案します。年収を維持・向上させながら、なぜ発注者支援業務がワークライフバランス(WLB)を実現しやすいのか、その具体的な理由と、あなたの技術的価値を維持・向上させる方法を解説していきましょう。
データで見る建設業界の労働時間と課題(2024年問題の影響)
建設業界の働き方改革は、単なる「努力目標」ではなく、法的な規制と業界の持続可能性に関わる喫緊の課題です。まずは、なぜ多くの施工管理者が疲弊してしまうのか、その背景をデータで確認しましょう。
建設業における慢性的な長時間労働と休日の不足
建設業における年間総実労働時間は、全産業平均と比べると、依然として高い水準にあります。
特に深刻なのは、休日取得の状況です。建設工事全体で見ると、約65%の事業所が4週4休以下で就業しているという事実が明らかになっています。現在、他産業では常識となっている4週8休を達成しているのは、残念ながら1割以下にとどまっています。技術者・技能者双方において、最も多い休日の取得状況が「4週6休程度」となっており、週休2日の確保がいかに困難であるかが浮き彫りになっています。
施工管理職の残業事情や平均時間についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
特に深刻なのは、休日取得の状況です。建設工事全体で見ると、約65%の事業所が4週4休以下で就業しているという事実が明らかになっています。現在、他産業では常識となっている4週8休を達成しているのは、残念ながら1割以下にとどまっています。技術者・技能者双方において、最も多い休日の取得状況が「4週6休程度」となっており、週休2日の確保がいかに困難であるかが浮き彫りになっています。
施工管理職の残業事情や平均時間についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
適切な賃金水準と工期設定の課題
長時間労働に加えて、建設業は賃金構造にも課題を抱えています。
建設業の平均年間賃金は417万円であり、これは全産業平均の494万円と比較して、低い水準にあります。また、小規模な事業所(1〜4人)の給与額は他の小規模産業より高い傾向にありますが、大規模な建設業の平均には及びません。これは、業界全体として、技術者の労務費を適切に反映させ、適正な賃金水準を確保することが重要な課題であることを示しています。
さらに、長時間労働の原因の一つとして、工期短縮のプレッシャーが挙げられます。工期短縮と長時間労働には相関関係があるため、建設業法第19条の5に基づき、注文者(発注者)は、通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結することが禁止されています。現在、受発注者間での工期に関する協議や合意形成が、働き方改革の重要な施策として推進されているところです。
建設業の平均年間賃金は417万円であり、これは全産業平均の494万円と比較して、低い水準にあります。また、小規模な事業所(1〜4人)の給与額は他の小規模産業より高い傾向にありますが、大規模な建設業の平均には及びません。これは、業界全体として、技術者の労務費を適切に反映させ、適正な賃金水準を確保することが重要な課題であることを示しています。
さらに、長時間労働の原因の一つとして、工期短縮のプレッシャーが挙げられます。工期短縮と長時間労働には相関関係があるため、建設業法第19条の5に基づき、注文者(発注者)は、通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結することが禁止されています。現在、受発注者間での工期に関する協議や合意形成が、働き方改革の重要な施策として推進されているところです。
罰則付き上限規制「2024年問題」の適用開始
そして、この業界の働き方に決定的な変革を迫るのが、2024年問題への対応です。
令和6年4月からは、建設業にもいよいよ罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されています。この規制では、時間外労働は原則として月45時間、年間360時間と定められており、これに違反した場合、罰則の対象となる可能性があります。
この法規制の適用は、建設業界に「働き方改革」の推進を強力に義務付けるものであり、技術者一人ひとりが自身のキャリアと働き方を見直すための、極めて重要なターニングポイントとなるでしょう。
令和6年4月からは、建設業にもいよいよ罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されています。この規制では、時間外労働は原則として月45時間、年間360時間と定められており、これに違反した場合、罰則の対象となる可能性があります。
この法規制の適用は、建設業界に「働き方改革」の推進を強力に義務付けるものであり、技術者一人ひとりが自身のキャリアと働き方を見直すための、極めて重要なターニングポイントとなるでしょう。
なぜ発注者支援業務はワークライフバランスを実現しやすいのか?
施工管理者がキャリアチェンジ先として、公的な発注者側の業務(発注者支援業務:調査・設計、積算、監督・検査等の発注関係事務を適切に実施する業務)を選択することは、長時間労働の是正とWLBの確保という観点から、非常に合理的な選択肢となります。
発注者支援業務の具体的な内容について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
公共工事における発注関係事務の品質確保は、豊かな国民生活の実現や社会資本の安全確保に寄与する、社会経済上重要な意義を持つため、その役割は法的に重視されています。
発注者支援業務の具体的な内容について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
公共工事における発注関係事務の品質確保は、豊かな国民生活の実現や社会資本の安全確保に寄与する、社会経済上重要な意義を持つため、その役割は法的に重視されています。
理由1:公的機関に準じた勤務形態とWLB推進策の適用
発注者支援業務がワークライフバランス(WLB)を実現しやすい最大の理由は、公的な勤務環境や規制遵守の枠組みの中で業務を遂行する点にあります。
発注者の責務
発注者である国や地方公共団体は、建設業法や品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)の基本理念に基づき、労働者の健康と安全に留意し、WLBを実現する働き方改革に関する施策を推進する責務があります。
公務員に準じた勤務形態
勤務先が国土交通省の出張所などの官公庁となるため、勤務時間や休日は公務員に準じます。
- 休日: 土日祝日の完全週休2日制が基本です。
- 就業時間: 「8時30分から17時15分」などが多く、施工管理のように朝早くから現場に出る必要はありません。
残業の傾向
繁忙期(特に年度末の1月〜3月)に残業が発生することもありますが、施工管理に比べると少ない傾向にあります。
発注者支援業務の残業状況に関する詳細は、こちらの記事をご覧ください。
発注者支援業務の残業状況に関する詳細は、こちらの記事をご覧ください。
長時間労働を抑制する具体的な施策
国土交通省の直轄工事においては、勤務時間外の作業を避ける「ウィークリースタンス」が徹底されており、休日や業務時間外に依頼や連絡を行わないことなどが、全ての工事・業務を対象に実施されています。
これらの公的な枠組みの中で計画的に業務を進めるため、結果的に長時間労働が抑制されやすく、WLBを意識した勤務が期待できます。
理由2:現場常駐からの解放とICTの積極的活用
従来の施工管理業務では、工事現場への常駐が長時間労働の大きな原因となっていましたが、発注者支援業務においては、ICT(情報通信技術)の活用による生産性向上が強力に推進されています。
現場技術者の専任義務の合理化
国は、現場技術者の専任義務の合理化を進めており、例えば兼任を容認する条件として、兼任する現場間の移動が容易であることや、ICTを活用した遠隔からの現場確認が可能であることなどが挙げられています。
デジタル化の強力な推進
国はCCUS(建設キャリアアップシステム)を活用した施工体制の「見える化」など、デジタル化を推進しています。
ICT活用による役割の変化
発注者側の業務は、これらのICT技術やデータ(CCUSの就業履歴や施工体制台帳など)を活用し、遠隔で工事の監督や確認を行う役割を担います。
これにより、技術者は従来の現場常駐の負荷から解放され、より効率的な業務遂行が可能となります。結果として、自宅やオフィスで計画的に仕事を進める時間が増えることになります。
理由3:計画的な業務進行と技術的検討
施工現場の管理では、天候不順や予期せぬトラブルなど突発的な対応が避けられませんが、発注者支援業務は計画的な技術的検討が業務の中心となります。
業務内容の特性
主となる業務は、調査・設計、積算、技術審査などです。
これらは現場での突発的な対応よりも、計画に基づいた技術的検討や評価、文書作成、協議が中心となります。
これらは現場での突発的な対応よりも、計画に基づいた技術的検討や評価、文書作成、協議が中心となります。
公共工事における品質確保の重要性
公共工事の品質確保を図る上で、調査及び設計の品質は極めて重要です。
発注者は、技術提案を求め、価格と品質が総合的に優れた内容の契約がなされるよう努める必要があります。
発注者は、技術提案を求め、価格と品質が総合的に優れた内容の契約がなされるよう努める必要があります。
厳格な評価プロセス
業務の履行過程や成果の評価においては、技術者の経験や成績評定結果を適切に審査・評価することが求められます。
このように、発注者支援業務は計画性と技術的な正確さが重視されるため、現場管理業務と比べて突発的な残業を抑制しやすい傾向にあると言えるでしょう。
年収を下げずに働き方を変える!技術的価値が評価される仕組み
施工管理から発注者支援業務へキャリアチェンジすることは、単に労働時間を削減するだけでなく、これまでの現場経験を活かし、技術者としての市場価値を維持・向上させるための戦略でもあります。
建設業界の平均年収が全産業平均を下回る中、「年収を維持・向上させつつ、働き方を変えたい」というニーズに対し、発注者支援業務はどのように応えるのでしょうか。
建設業界の平均年収が全産業平均を下回る中、「年収を維持・向上させつつ、働き方を変えたい」というニーズに対し、発注者支援業務はどのように応えるのでしょうか。
1. 技術的能力が審査される入札・契約制度
公共工事の契約では、発注者は単に価格が安い業者を選ぶのではなく、価格以外の多様な要素(工事実績、施工状況の評価、配置予定技術者の経験等)を考慮して、価格と品質が総合的に優れた内容の契約を結ぶことが基本理念とされています。
発注者支援業務の主要領域である調査・設計の契約においても、発注者は競争参加者に対し技術提案を求め、その技術的能力を審査します。さらに、技術者の経験やその成績評定結果を適切に審査・評価することが求められるのです。
つまり、発注者支援業務では、現場で培ってきた高い技術力と豊富な経験が、単なる労働時間ではなく、客観的な技術的価値として正当に評価される機会が得られるということです。
発注者支援業務の主要領域である調査・設計の契約においても、発注者は競争参加者に対し技術提案を求め、その技術的能力を審査します。さらに、技術者の経験やその成績評定結果を適切に審査・評価することが求められるのです。
つまり、発注者支援業務では、現場で培ってきた高い技術力と豊富な経験が、単なる労働時間ではなく、客観的な技術的価値として正当に評価される機会が得られるということです。
2. 資格取得による市場価値の最大化
現場で積み上げた経験が技術者としての「血肉」であるとすれば、それを客観的に証明し、市場価値を飛躍的に高めるための「鎧」が「資格」です。発注者支援業務において、資格は転職や昇進、そして高年収を目指す上で欠かせない要素です。
特に、1級施工管理技士の資格はスタートラインとして非常に重要であり、大規模工事で配置が義務付けられる「監理技術者」を担えるため、高単価な案件への道が拓けます。さらに資格保有は、企業の技術力評価点を押し上げるため、資格手当(月額5,000円〜20,000円以上)といった形で直接的な収入増にも繋がるのです。
1級土木施工管理技士がもたらすメリットについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
さらに高みを目指すなら、科学技術分野における最高位の国家資格である「技術士(建設部門)」や、建設コンサルタント業務の管理・照査技術者としての能力を証明する「RCCM(シビルコンサルティングマネージャー)」といった上位資格が視野に入ります。
特に、1級施工管理技士の資格はスタートラインとして非常に重要であり、大規模工事で配置が義務付けられる「監理技術者」を担えるため、高単価な案件への道が拓けます。さらに資格保有は、企業の技術力評価点を押し上げるため、資格手当(月額5,000円〜20,000円以上)といった形で直接的な収入増にも繋がるのです。
1級土木施工管理技士がもたらすメリットについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
さらに高みを目指すなら、科学技術分野における最高位の国家資格である「技術士(建設部門)」や、建設コンサルタント業務の管理・照査技術者としての能力を証明する「RCCM(シビルコンサルティングマネージャー)」といった上位資格が視野に入ります。
3. 技術提案に伴う適切な価格設定
発注関係事務において高度な専門知識や技術的な裏付けが求められる調査・設計段階では、技術的な優位性が直接的に報酬につながる仕組みも存在します。
発注者は、高度な技術や優れた工夫を含む技術提案を求めた場合、その技術提案の審査結果を踏まえて、最も優れた提案が採用できるよう予定価格を定めることができるとされています。
これは、質の高い技術提案を行うことで、それが適切な報酬や対価として反映されることを示唆しており、単なる労働集約的な働き方ではなく、技術的な付加価値によって年収を維持・向上させることが可能であることを裏付けていると言えるでしょう。
発注者は、高度な技術や優れた工夫を含む技術提案を求めた場合、その技術提案の審査結果を踏まえて、最も優れた提案が採用できるよう予定価格を定めることができるとされています。
これは、質の高い技術提案を行うことで、それが適切な報酬や対価として反映されることを示唆しており、単なる労働集約的な働き方ではなく、技術的な付加価値によって年収を維持・向上させることが可能であることを裏付けていると言えるでしょう。
まとめ:キャリアチェンジで手に入れる、仕事と人生の新しいバランス
2024年問題の適用により、建設業は、時間外労働の上限規制に対応するため、労働者の処遇確保や働き方改革、生産性向上に総合的に取り組むことが不可欠となっています。
建設業が将来にわたり「地域の守り手」としての役割を果たし、持続可能な産業となるためには、「給与がよい、休日がとれる、希望がもてる、カッコイイ」という「新4K」の実現が重要です。
発注者支援業務というキャリアの選択は、まさにこの「新4K」のうち、「休日がとれる」「希望がもてる」を実現するための、現実的な手段なのです。
施工管理からの転職を成功させるためのポイントについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
このキャリアシフトによって、あなたは以下のような新しいバランスを手に入れることができます。
発注者支援業務というキャリアの選択は、まさにこの「新4K」のうち、「休日がとれる」「希望がもてる」を実現するための、現実的な手段なのです。
施工管理からの転職を成功させるためのポイントについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
このキャリアシフトによって、あなたは以下のような新しいバランスを手に入れることができます。
- 公的環境でのWLB実現: 国や自治体の働き方改革施策が適用されやすい環境で、長時間労働が抑制されます。計画的な勤務が可能になることで、家族やプライベートの時間を確保できます。
- 技術力の維持・向上: 調査・設計、積算、技術審査といった高度な発注関係事務を通して、これまでの知識と経験を最大限に活かせます。技術提案や評価の能力が求められるため、技術者としての市場価値をむしろ維持・向上させることが可能です。
- デジタル化への適応: ICTツールを活用した現場管理や遠隔確認のスキルを習得することで、デジタル化が進む建設業界の将来にわたる変化に柔軟に適応できるようになります。
「現場の施工管理」から「発注関係事務の支援」へキャリアをシフトすることは、2024年問題以降の建設業界において、技術者としての知識と経験を最大限に活かしつつ、私生活や家庭との調和を取り戻すための、現実的かつ前向きなキャリア戦略なのです。
もし今、「現場か、家庭か」の選択に悩んでいるのであれば、あなたの長年の経験と技術力が必要とされている、発注者支援という新しいフィールドへ、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。これが、仕事と人生の新しいバランスを手に入れるための、最良の選択肢となるかもしれません。
もし今、「現場か、家庭か」の選択に悩んでいるのであれば、あなたの長年の経験と技術力が必要とされている、発注者支援という新しいフィールドへ、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。これが、仕事と人生の新しいバランスを手に入れるための、最良の選択肢となるかもしれません。
ワークライフバランスを求めて発注者支援業務での転職を目指すなら!
求人情報を要チェック!
\\求人情報は毎日更新中//