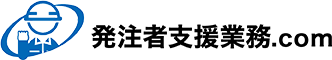2025-10-31建設情報コラム
1級土木施工管理技士の年収は本当に低いのか?実態とキャリア戦略を徹底解説
1級土木施工管理技士の年収について「低い」という声を耳にすることがありますが、実際のところはどうなのでしょうか。
このセクションでは、各種調査データをもとに、1級土木施工管理技士の年収を多角的に検証していきます。
日本全体の平均年収や他の施工管理技士との比較、さらには年齢別・企業規模別の格差まで、具体的な数値をもとに実態を明らかにします。
このセクションでは、各種調査データをもとに、1級土木施工管理技士の年収を多角的に検証していきます。
日本全体の平均年収や他の施工管理技士との比較、さらには年齢別・企業規模別の格差まで、具体的な数値をもとに実態を明らかにします。
1級土木施工管理技士の年収は本当に低いのか?データで検証
1級土木施工管理技士の平均年収について、最も信頼できるデータは厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」です。
厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」によると、建設業で働く技術者の賃金は以下の通りです。
厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」によると、建設業で働く技術者の賃金は以下の通りです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 平均月収(所定内給与額) | 約35.3万円 |
| 年間給与(月収×12ヶ月) | 約423万円 |
| 推定年間賞与 | 約141万円 |
| 推定平均年収 | 約564万円 |
※出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」
※年収は所定内給与額×12ヶ月+年間賞与(約4ヶ月分)で算出
この金額には1級・2級土木施工管理技士や、資格を持たない土木技術者も含まれていますが、1級土木施工管理技士は資格手当や役職手当が加算されるため、この水準かそれ以上の年収が期待できます。
また、令和6年調査では、建設業の賃金は対前年比で0.9%増加しており、緩やかながらも上昇傾向にあることがわかります。これは建設業界全体の人手不足を背景とした賃金改善の動きを反映しています。
1級土木施工管理技士の難易度について詳しく知りたい方はこちらの記事で解説しています。
※年収は所定内給与額×12ヶ月+年間賞与(約4ヶ月分)で算出
この金額には1級・2級土木施工管理技士や、資格を持たない土木技術者も含まれていますが、1級土木施工管理技士は資格手当や役職手当が加算されるため、この水準かそれ以上の年収が期待できます。
また、令和6年調査では、建設業の賃金は対前年比で0.9%増加しており、緩やかながらも上昇傾向にあることがわかります。これは建設業界全体の人手不足を背景とした賃金改善の動きを反映しています。
1級土木施工管理技士の難易度について詳しく知りたい方はこちらの記事で解説しています。
日本の平均年収との比較
では、この564万円という年収は、日本全体の年収と比較してどうなのでしょうか。
| 分類 | 平均年収 | 出典 |
|---|---|---|
| 建設業技術者 | 約564万円 | 厚生労働省(令和6年) |
| 建設業全体 | 約565万円 | 厚生労働省(令和6年) |
| 日本人全体 | 約458万円 | 国税庁(令和5年) |
このデータから、以下の事実が明らかになります。
建設業技術者の年収は日本の平均を約100万円上回っています。
建設業技術者の年収564万円は、日本人全体の平均年収458万円と比較すると、約106万円(約23%)も高い水準です。
また、建設業全体の平均565万円とほぼ同水準であり、業界内でも標準的な給与水準にあることがわかります。
数値だけ見れば「低い」とは言えない
客観的なデータで見る限り、1級土木施工管理技士の年収は決して「低い」とは言えません。むしろ、日本全体の中では高収入の部類に入ります。
それでも「年収が低い」と感じる人がいるのは、後述する労働時間や企業規模による格差、取得難易度とのバランスなど、複合的な要因が関係しています。
それでも「年収が低い」と感じる人がいるのは、後述する労働時間や企業規模による格差、取得難易度とのバランスなど、複合的な要因が関係しています。
1級土木施工管理技士の年収が「低い」と感じる5つの理由
データ上は決して低くない1級土木施工管理技士の年収ですが、なぜ「低い」と感じる人がいるのでしょうか。
このセクションでは、年収に対する不満の背景にある5つの具体的な理由を分析します。
取得難易度と年収のバランス、労働時間の実態、企業による待遇の差など、現場で働く技術者の実感に基づいた課題を明らかにしていきます。
こちらの記事では、一級土木施工管理技士を取得するメリットを詳しく解説しています。
気になる方はチェックしてみましょう。
このセクションでは、年収に対する不満の背景にある5つの具体的な理由を分析します。
取得難易度と年収のバランス、労働時間の実態、企業による待遇の差など、現場で働く技術者の実感に基づいた課題を明らかにしていきます。
こちらの記事では、一級土木施工管理技士を取得するメリットを詳しく解説しています。
気になる方はチェックしてみましょう。
理由①:取得までの長い道のりと難易度に見合わない
1級土木施工管理技士の資格取得には、想像以上の時間と労力が必要です。
この「投資」に対して、年収という「リターン」が見合っていないと感じる人が少なくありません。
【資格取得までのハードル】
この「投資」に対して、年収という「リターン」が見合っていないと感じる人が少なくありません。
【資格取得までのハードル】
- 実務経験の長さ:1級土木施工管理技士の受験には、学歴に応じて3年~15年以上の実務経験が必要です(令和6年度以降は第一次検定のみ実務経験不要に緩和)
- 試験の難易度:合格率は第一次検定が約40~50%、第二次検定が約30~40%と決して高くありません
- 勉強時間の確保:現場作業と並行して数百時間の勉強が必要になります
- 受験費用:受験料、参考書、通信講座などで10万円以上かかるケースも珍しくありません
これだけの時間とコストをかけて資格を取得しても、年収が50万円~100万円程度しか上がらない企業もあります。
特に中小企業では資格手当が月額1万円以下というケースもあり、「こんなに苦労したのに…」という失望感につながりやすいのです。
特に中小企業では資格手当が月額1万円以下というケースもあり、「こんなに苦労したのに…」という失望感につながりやすいのです。
仮に資格取得にかかった費用が15万円、勉強時間が500時間(時給2,000円換算で100万円相当)だとすると、総投資額は約115万円です。
資格取得後の年収アップが年間30万円だった場合、投資を回収するまでに約4年かかる計算になります。
この期間を「長い」と感じるかどうかは個人差がありますが、IT業界などでは資格取得後すぐに大幅な年収アップが期待できるケースも多く、比較すると見劣りすると感じる人もいるでしょう。
資格取得後の年収アップが年間30万円だった場合、投資を回収するまでに約4年かかる計算になります。
この期間を「長い」と感じるかどうかは個人差がありますが、IT業界などでは資格取得後すぐに大幅な年収アップが期待できるケースも多く、比較すると見劣りすると感じる人もいるでしょう。
理由②:労働時間の長さを考慮すると時給が低い
建設業界、特に施工管理の仕事は長時間労働になりがちです。
年収の額面だけでなく、労働時間を考慮した「実質的な時給」で考えると、他業種より低くなる可能性があります。
土木施工管理技士の典型的な労働時間を見てみましょう。
【建設業の労働時間の実態】
年収の額面だけでなく、労働時間を考慮した「実質的な時給」で考えると、他業種より低くなる可能性があります。
土木施工管理技士の典型的な労働時間を見てみましょう。
【建設業の労働時間の実態】
- 月間所定労働時間:約160時間(週40時間×4週)
- 残業時間:月50~80時間(工期が迫る時期はさらに増加)
- 休日出勤:月2~4日程度
- 早朝出勤:朝礼や現場確認のため、6時~7時出社も珍しくない
年収500万円の1級土木施工管理技士が月80時間の残業をしている場合を計算してみます。
- 年間総労働時間:(160時間 + 80時間)× 12ヶ月 = 2,880時間
- 実質時給:500万円 ÷ 2,880時間 = 約1,736円
一方、年収450万円で残業がほとんどない職種の場合は、以下のような時給計算になります。
- 年間総労働時間:160時間 × 12ヶ月 = 1,920時間
- 実質時給:450万円 ÷ 1,920時間 = 約2,344円
このように、労働時間を考慮すると、年収が高くても実質的な時給は低くなってしまうケースがあります。
さらに、施工管理の仕事は精神的なストレスも大きく、現場の安全管理や工程管理といった責任の重さを考えると、「割に合わない」と感じる人がいるのも無理はありません。
さらに、施工管理の仕事は精神的なストレスも大きく、現場の安全管理や工程管理といった責任の重さを考えると、「割に合わない」と感じる人がいるのも無理はありません。
理由③:中小企業では資格手当が十分でない
同じ1級土木施工管理技士の資格を持っていても、勤務先の企業規模によって資格手当の額は大きく異なります。
【企業規模別の資格手当の相場】
【企業規模別の資格手当の相場】
| 企業規模 | 1級土木施工管理技士の資格手当(月額) | 年間の手当額 |
|---|---|---|
| スーパーゼネコン | 3万円~5万円 | 36万円~60万円 |
| 準大手ゼネコン | 2万円~4万円 | 24万円~48万円 |
| 地場中堅企業 | 1万円~2万円 | 12万円~24万円 |
| 中小企業 | 5千円~1万円(またはなし) | 6万円~12万円 |
中小企業の中には、資格手当の制度自体が存在しないケースもあります。「1級を取得しても給料がほとんど変わらなかった」という声が聞かれるのは、このような企業で働いている場合が多いのです。
また、大手企業では1級土木施工管理技士の資格が昇進の必須条件となっていることが多く、資格取得が管理職へのステップとなります。
しかし、中小企業では資格の有無よりも実務経験や人間関係が重視されるケースもあり、資格を取得しても必ずしも昇進につながるわけではありません。
企業選びの段階で、資格手当の制度や資格取得者の処遇について確認することが重要です。
求人票に「資格手当あり」と書かれていても、具体的な金額が明記されていない場合は、面接時にしっかり確認しましょう。
理由④:賃金ピークが早く、スキルが評価されにくい
建設業特有の問題として、賃金のピーク時期が他業種より早いという点があります。
【賃金カーブの比較】
【賃金カーブの比較】
- 建設業:45~49歳でピーク(平均年収約650万円)
- 製造業:50~54歳でピーク(平均年収約700万円)
建設業では40代前半でピーク水準に到達し、それ以降は横ばいまたは微減する傾向があります。
これは、現場での管理能力や後進の指導といったスキルが、給与に十分反映されていない可能性を示唆しています。
1級土木施工管理技士として豊富な経験を持ち、若手の育成や複雑な現場の統括ができるようになっても、50代以降は年収が大きく伸びないのが実情です。
むしろ、60代に入ると定年再雇用の影響で年収が大幅に下がるケースが一般的です。
これは、現場での管理能力や後進の指導といったスキルが、給与に十分反映されていない可能性を示唆しています。
1級土木施工管理技士として豊富な経験を持ち、若手の育成や複雑な現場の統括ができるようになっても、50代以降は年収が大きく伸びないのが実情です。
むしろ、60代に入ると定年再雇用の影響で年収が大幅に下がるケースが一般的です。
- 40代後半:平均年収約650万円
- 50代前半:平均年収約680万円(ピーク)
- 50代後半:平均年収約650万円
- 60代前半:平均年収約450万円(再雇用)
他業種では管理職として60代でも高い年収を維持できるケースがありますが、建設業では体力的な面や現場主体の働き方から、年齢とともに年収が下がりやすい構造になっています。
長年培ってきた技術や知識が適切に評価され、年収に反映される仕組みの構築が業界全体の課題といえるでしょう。
長年培ってきた技術や知識が適切に評価され、年収に反映される仕組みの構築が業界全体の課題といえるでしょう。
理由⑤:他業界(IT・金融等)と比較して見劣りする
同世代の友人や同級生と比較したときに、「自分の年収は低いのでは?」と感じる人も少なくありません。
例えば、大卒で同時期にIT業界で社会人となった場合を比較してみましょう。
例えば、大卒で同時期にIT業界で社会人となった場合を比較してみましょう。
| 年齢・経験年数 | 1級土木施工管理技士 | IT技術者(システムエンジニア) |
|---|---|---|
| 20代(入社3~5年目) | 350万円~420万円 | 400万円~500万円 |
| 30代前半(入社7~10年目) | 500万円~550万円 | 550万円~700万円 |
| 30代後半(入社12~15年目) | 550万円~600万円 | 650万円~900万円 |
| 40代(管理職クラス) | 600万円~700万円 | 800万円~1,200万円 |
大卒初任給は両業界ともほぼ同等(21万円~23万円程度)ですが、30代以降の年収の伸びに大きな差が出てきます。
IT業界では、プロジェクトマネージャーやスペシャリストとして高い評価を受けると、30代で年収800万円以上も珍しくありません。
若い世代が職業を選ぶ際、年収は重要な判断基準の一つです。
他業界と比較して年収の伸びが限定的であることが、建設業界への若手人材の流入を阻害している一因となっている可能性があります。
ただし、建設業には以下のような他業界にはない魅力もあります。
- 自分の仕事が形として残り、社会インフラに貢献できる
- 資格さえあれば年齢に関係なく転職しやすい
- 全国どこでも仕事がある
- AIに代替されにくい
年収だけでなく、こうした仕事の意義ややりがいも含めて、総合的にキャリアを考えることが大切です。
1級土木施工管理技士として年収アップを実現する3つの方法
年収に不満を感じている、あるいはこれから資格を取得して高い年収を目指したいという方に向けて、具体的な年収アップの方法をご紹介します。
このセクションでは、転職、資格取得、技術習得という3つの選択肢について、それぞれのメリットや実現方法を詳しく解説していきます。
自分の状況やキャリアプランに合った方法を見つける参考にしてください。
1級土木施工管理技士の勉強時間については、こちらの記事で確認できます。
このセクションでは、転職、資格取得、技術習得という3つの選択肢について、それぞれのメリットや実現方法を詳しく解説していきます。
自分の状況やキャリアプランに合った方法を見つける参考にしてください。
1級土木施工管理技士の勉強時間については、こちらの記事で確認できます。
方法①:大手ゼネコン・準大手への転職を検討する
最も確実かつ大幅な年収アップが期待できるのが、大手ゼネコンや準大手ゼネコンへの転職です。
| 企業タイプ | 平均年収 | 代表的な企業例 |
|---|---|---|
| スーパーゼネコン | 900万円~1,100万円 | 鹿島建設、大林組、清水建設 大成建設、竹中工務店 |
| 準大手ゼネコン | 800万円~900万円 | 長谷工コーポレーション、フジタ 五洋建設、戸田建設、前田建設工業 |
| 地場中堅ゼネコン | 600万円~800万円 | 各地域の有力建設会社 |
| 中小建設会社 | 450万円~600万円 | 地域密着型の建設会社 |
中小企業から大手ゼネコンに転職できれば、年収が200万円~400万円以上アップすることも珍しくありません。
しかし、転職で成功するためには、タイミングが重要です。
- 20代後半~30代前半:最も転職市場で評価されやすい年代。1級資格取得直後が狙い目
- 30代後半~40代前半:現場所長経験があれば高く評価される。大規模プロジェクトの経験が武器に
- 40代後半以降:管理職としての実績や人脈が重視される。部門長クラスでの採用も
一般的に、30代での転職が最も年収アップ幅が大きくなる傾向があります。
2級から1級にステップアップしたタイミングで、大手企業への転職を検討するのも一つの戦略です。
【大手ゼネコンが求めるスキル・経験】
2級から1級にステップアップしたタイミングで、大手企業への転職を検討するのも一つの戦略です。
【大手ゼネコンが求めるスキル・経験】
- 1級土木施工管理技士の資格(必須)
- 大規模工事(10億円以上)の施工管理経験
- 橋梁、トンネル、ダムなど専門性の高い工事の経験
- 発注者との折衝能力
- チームマネジメント経験
- 安全管理の実績(無事故記録など)
これらの経験を履歴書や面接でしっかりアピールできれば、大手企業からのオファーを獲得できる可能性が高まります。
転職エージェントを活用して、自分の強みを最大限に引き出す戦略を立てましょう。
転職エージェントを活用して、自分の強みを最大限に引き出す戦略を立てましょう。
方法②:関連資格を取得して専門性を高める
1級土木施工管理技士に加えて関連資格を取得することで、専門性を高め、年収アップにつなげることができます。
【年収アップに効果的な関連資格】
【年収アップに効果的な関連資格】
- 測量士・測量士補:測量業務にも対応できる技術者として評価される。資格手当:月5千円~1万円
- コンクリート技士・診断士:構造物の品質管理に強みを持つ。資格手当:月5千円~1万5千円
- 技術士(建設部門):最高峰の技術資格。大幅な年収アップが期待できる。資格手当:月2万円~5万円
- RCCM(シビルコンサルティングマネージャー):設計・コンサルタント業務にも対応可能。資格手当:月1万円~3万円
- 土木鋼構造診断士:橋梁などの鋼構造物に特化した専門性。資格手当:月1万円~2万円
複数の資格を保有することで、資格手当が積み重なります。
例えば、以下のようなケースです。
例えば、以下のようなケースです。
- 1級土木施工管理技士:月3万円
- コンクリート技士:月1万円
- 測量士:月5千円
- 合計:月4万5千円(年間54万円)
中小企業では個別の資格手当が少なくても、複数資格の合計で大きな金額になる場合があります。
また、資格を多く持っていること自体が、技術者としての市場価値を高め、転職時の交渉材料になります。
また、転職市場では、1級土木施工管理技士だけを持っている人よりも、複数の関連資格を保有している人の方が高く評価されます。
特に、技術士やRCCMといった難関資格を持っていると、コンサルタント業務や設計業務にも対応できる人材として、より幅広い求人にアプローチできるようになります。
資格取得には時間と費用がかかりますが、長期的なキャリア形成の観点から見れば、確実にリターンが得られる投資といえるでしょう。
資格取得支援制度(受験料補助、勉強時間の配慮など)が充実している企業を選ぶことも、効率的に複数資格を取得する上で重要です。
また、資格を多く持っていること自体が、技術者としての市場価値を高め、転職時の交渉材料になります。
また、転職市場では、1級土木施工管理技士だけを持っている人よりも、複数の関連資格を保有している人の方が高く評価されます。
特に、技術士やRCCMといった難関資格を持っていると、コンサルタント業務や設計業務にも対応できる人材として、より幅広い求人にアプローチできるようになります。
資格取得には時間と費用がかかりますが、長期的なキャリア形成の観点から見れば、確実にリターンが得られる投資といえるでしょう。
資格取得支援制度(受験料補助、勉強時間の配慮など)が充実している企業を選ぶことも、効率的に複数資格を取得する上で重要です。
方法③:ICT・BIM/CIM技術を習得する
建設業界でもデジタル化が急速に進んでおり、ICT(情報通信技術)やBIM/CIM(建設情報モデリング)の技術を持つ人材の需要が高まっています。
国土交通省は「i-Construction」として、建設現場の生産性向上を推進しており、以下のような技術が注目されています。
国土交通省は「i-Construction」として、建設現場の生産性向上を推進しており、以下のような技術が注目されています。
- ICT施工:ドローン測量、3次元設計データ、情報化施工機械の活用
- BIM/CIM:3次元モデルを活用した設計・施工・維持管理
- 遠隔臨場:Web会議システムを使った現場確認
- 電子小黒板:工事写真の電子化
- 施工管理アプリ:タブレットやスマートフォンを使った現場管理
これらの技術を使いこなせる土木施工管理技士は、従来型の技術者と差別化でき、より高い評価を受けられます。
デジタル技術に精通した土木施工管理技士の給与は、従来型の技術者と比べて以下のような差が出ています。
デジタル技術に精通した土木施工管理技士の給与は、従来型の技術者と比べて以下のような差が出ています。
| 技術レベル | 平均年収 | 従来型技術者との差 |
|---|---|---|
| ICT・BIM/CIM活用スキルなし | 500万円 | - |
| 基本的な活用ができる | 550万円 | +50万円 |
| 高度な活用・指導ができる | 650万円~800万円 | +150万円~300万円 |
特に大手ゼネコンでは、ICT施工を推進できる人材を積極的に採用しており、高い給与を提示するケースが増えています。
デジタル技術を習得するには、以下のような方法があります。
- 公的機関の講習:国土交通省や建設業振興基金が実施する研修プログラム(無料~数万円)
- メーカー主催の講習:建設機械メーカーやソフトウェア会社が提供する技術講習
- 実務での経験:ICT施工の現場に配属してもらい、OJTで学ぶ
- オンライン学習:YouTubeやUdemyなどでBIM/CIMの基礎を学ぶ
40代、50代の技術者でも、デジタル技術を積極的に学ぶ姿勢を持つことで、若手との差別化を図り、定年まで高い年収を維持できる可能性が高まります。
まとめ:1級土木施工管理技士の年収は「低くない」が戦略的なキャリア形成が重要
ここまで見てきたように、1級土木施工管理技士の年収は、データで見れば決して「低い」とは言えません。日本全体の平均年収を30万円~160万円程度上回っており、建設業の中でも平均的な水準にあります。
しかし、取得難易度の高さや長時間労働、企業規模による格差などを考慮すると、「期待していたより低い」と感じる人がいることも事実です。年収に対する満足度は、単純な金額だけでなく、労働環境や将来性、仕事のやりがいなど、さまざまな要素によって決まります。
重要なのは、企業選びとキャリア戦略次第で年収は大きく変わるということです。中小企業で年収500万円に留まるか、大手ゼネコンで年収1,000万円を目指すかは、あなたの選択と行動によって決まります。
1級土木施工管理技士という資格は、適切に活用すれば高い年収とやりがいのある仕事の両方を手に入れられる、価値ある資格です。戦略的にキャリアを形成し、充実した職業人生を送ってください。
しかし、取得難易度の高さや長時間労働、企業規模による格差などを考慮すると、「期待していたより低い」と感じる人がいることも事実です。年収に対する満足度は、単純な金額だけでなく、労働環境や将来性、仕事のやりがいなど、さまざまな要素によって決まります。
重要なのは、企業選びとキャリア戦略次第で年収は大きく変わるということです。中小企業で年収500万円に留まるか、大手ゼネコンで年収1,000万円を目指すかは、あなたの選択と行動によって決まります。
1級土木施工管理技士という資格は、適切に活用すれば高い年収とやりがいのある仕事の両方を手に入れられる、価値ある資格です。戦略的にキャリアを形成し、充実した職業人生を送ってください。
1級土木施工管理技士の資格で今すぐ活躍したい方は!
求人情報を要チェック!
\\求人情報は毎日更新中//